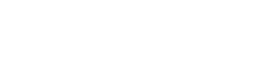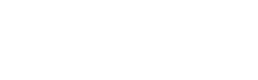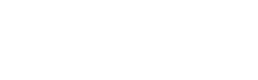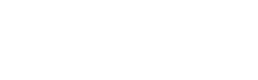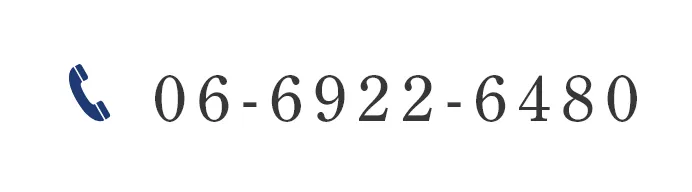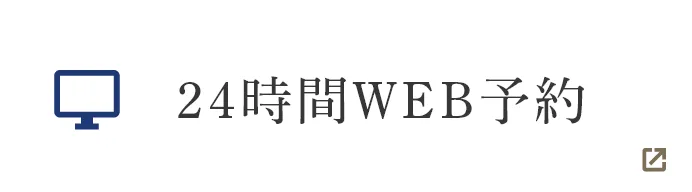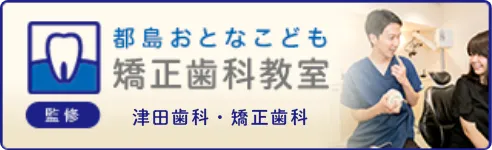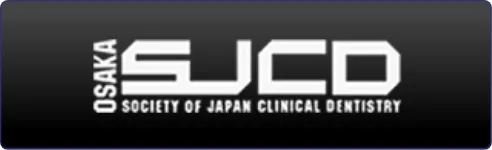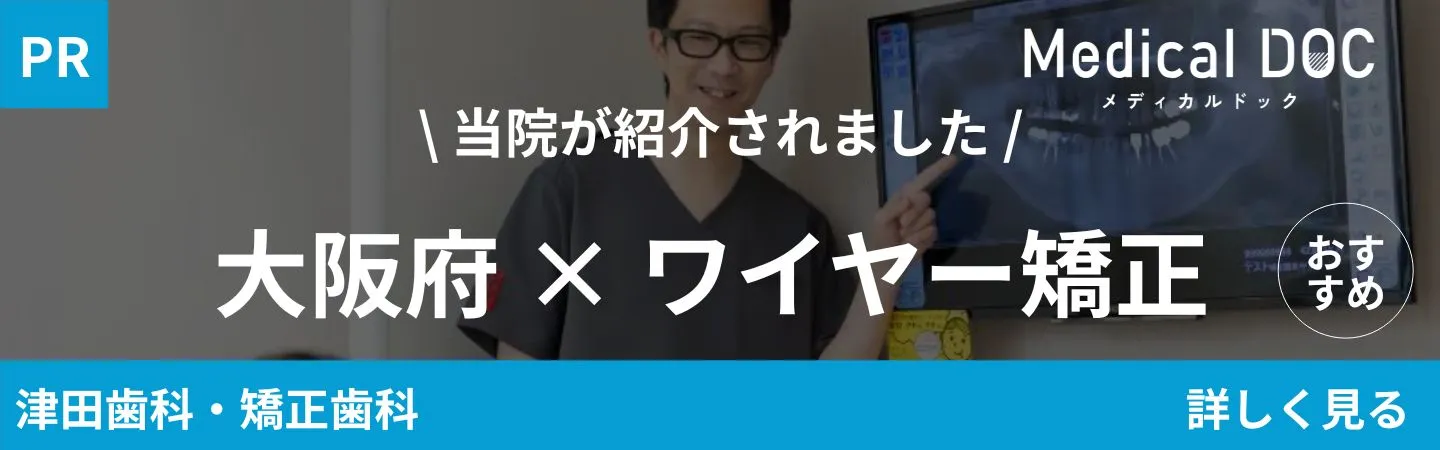スタッフブログ
「矯正治療で抜歯が必要な理由とは?歯を抜かずに治せるケースとの違いも解説|津田歯科・矯正歯科(大阪市都島区)」
矯正治療は、歯並びや口元を整えるだけでなく、長期的な機能性と審美性を両立させることが目的です🦷
歯を動かす際には「顎の大きさ」「歯の大きさ」「歯槽骨や軟組織の限界」を考慮する必要があります。
このバランスが取れていない場合、スペースを確保する手段として「抜歯」が選択されます。
無理に抜歯せずに矯正治療を行なった場合、口元の突出感や歯の前突感が改善されないなどの審美的な問題点や歯肉退縮などの機能的な問題を引き起こすことになります。
現在一般歯科医でも治療を盛んに行っているマウスピース矯正ではその特性上、抜歯矯正において難易度が急激に上がるため、本来は抜歯を必要とする症例を無理に非抜歯で治療を行う傾向があります。
中には矯正の専門的な知識のないままメーカーが指定したやり方で大きく失敗しているケースも多くご相談いただきます。
高価な費用を支払って行う矯正治療を失敗しないように慎重に歯科医院選びをしていただきたいと思っております。
次のような場合に抜歯を選択することがあります。
- 顎と歯の大きさの不調和(Arch length discrepancy)
矯正治療で最も頻繁に抜歯が行われる理由は、「顎の大きさに対して歯が大きすぎる」ことです。
- 歯列のアーチの長さ(arch length)と、全ての歯を並べるために必要なスペース(tooth material)の間に不一致があると、歯は叢生(ガタガタ)になります。
- 成長期の患者であれば拡大装置や成長誘導で改善できる場合もありますが、成人では骨格的な成長余地が限られます。
- 軽度のスペース不足(4mm以内程度)なら非抜歯で可能な場合もありますが、中等度〜高度(7mm以上)の場合は無理に歯列を拡大すると歯槽骨から歯根が逸脱し、歯肉退縮や骨吸収を引き起こすリスクが高まります。
例
顎の長さが90mmなのに対し、歯列を並べるのに95mm必要な場合、5mmの不足があります。この不足分を確保するには、歯を後方移動する・歯列を拡大する・歯を削る・抜歯する、などの方法が考えられますが、安全性・安定性を考慮すると抜歯が選択されることがあります。
- 前突の改善(口元の突出感)
日本人を含むアジア人は骨格的に鼻や下顎が欧米人よりも小さい傾向があり、歯が全て並んでいても口元が前に出て見えることがあります。
- 上下顎前歯が前方に傾斜し、口唇が閉じにくい「口唇閉鎖不全」や「E-lineから大きく前方に位置する口唇」などは、審美的にも機能的にも改善が必要です。
- 前歯を後退させるためには後方スペースが必要であり、これを確保する方法の一つが抜歯です。
典型例として、上下顎左右の第一小臼歯(4本)を抜歯し、そのスペースを利用して前歯全体を後方移動します。これにより口唇の突出感が軽減され、口元のバランスが整います。
- 咬合関係の改善(Class II・Class III などの不正咬合)
骨格的な不正咬合に加え、歯性の位置関係の改善のために抜歯が必要になることがあります。
- 上顎前突(Class II)
上顎の第一小臼歯を抜歯して上顎前歯を後方移動させることで、下顎との咬合関係を整える。 - 反対咬合(Class III)
下顎前歯の後退が必要な場合、下顎第一小臼歯を抜歯して下顎前歯を後方移動させる。 - 片側のみの抜歯
片側だけClass IIやIIIの傾向がある場合、片側のみ抜歯して非対称な咬合関係を改善する。
- 歯の位置異常や萌出障害
歯が本来の位置に萌出できず、著しく外れた位置にある場合(例:犬歯の高位唇側転位)、隣接歯を抜歯してスペースを確保することがあります。
また、過剰歯や歯の形態異常によってスペースが確保できない場合も抜歯が適応されます。
- 後戻り防止と安定性
無理に非抜歯で歯列を拡大・配列した場合、治療後に元の位置に戻ろうとする「後戻り」が生じやすくなります。これは歯周組織の形態的限界や筋圧のバランスが原因です。
- 抜歯してスペースを確保し、歯を骨の中心に近い位置へ移動させることで、安定性が高まります。
- 軟組織の限界と健康面への配慮
歯を歯槽骨の外まで動かして並べると、歯肉退縮や骨吸収が起こるリスクがあります。特に薄い歯肉・歯槽骨を持つ患者ではこのリスクが高く、将来的な知覚過敏や動揺の原因になります。
抜歯によって安全にスペースを作ることは、歯列矯正の長期的予後のためにも重要です。
抜歯か非抜歯かの判断基準
実際の臨床では、以下の要素を総合的に評価して判断します。
- スペース不足の量
- 軽度(〜4mm):削合(IPR)や拡大で対応
- 中等度(5〜7mm):症例により抜歯か非抜歯かを検討
- 高度(8mm以上):抜歯の適応が高い
- 側貌(口元の突出感)
- 審美的改善が必要なら抜歯の可能性が高まる
- 咬合関係
- クラスII・IIIの不正咬合では、抜歯でのスペース活用が有効
- 歯周組織の健康
- 歯槽骨や歯肉の厚み・形態を評価し、安全域を超えない移動計画を立てる
抜歯部位の選択
最も多いのは第一小臼歯の抜歯(犬歯の一つ後ろの歯)です。理由は以下の通り:
- 前歯と臼歯の中間にあり、スペースの利用が効率的
- 咬合の安定性を損なわずにスペースが得られる
- 抜歯による審美的変化がコントロールしやすい
その他、第二小臼歯・下顎切歯・臼歯の抜歯が選択されることもあります。当院では失活歯(神経をとった歯)を優先的に抜歯部位に選択することが多いです。これは失活歯が天然歯と比較して予後が悪いためです。健康な歯を矯正治療のために抜いて、失活歯が残っているのはできれば避けたいものです。また、親知らずが残ってる場合には親知らずを代わりに使用する場合もありますので、安易に抜歯を選択されないようにして下さい。
抜歯のメリットとデメリット
メリット
- 必要なスペースを安全に確保
- 歯並び・口元の審美的改善
- 歯周組織の健康維持
- 治療後の安定性向上
デメリット
- 健全な歯を失う:親知らずを除外して人間の歯は通常28本存在します。
4本抜歯すれば比較的噛み合わせに影響しにくい歯であったとしても
24本にはなっていますので、そこから何本か歯を失った場合には28本の方よりも噛み合わせは安定しにくい状態になります。矯正治療を行なった場合にはその後ご自身の歯は大切にしましょう!
- 治療期間がやや長くなる可能性
一般的に抜歯をした際の矯正治療期間は2.5年から3年程度かかります。矯正治療期間中に結婚式等のイベントでどうしてもワイヤーを外して欲しい時には一時的にワイヤーやブラケットを外し(費用が発生します)、またその後すぐに装着し矯正治療を再開することも可能です。
- 抜歯による外科的侵襲(腫れや痛み)
一般的に矯正治療のために便宜的に歯を抜歯した際にあまり腫れることはありません。ただ痛みはありますので、鎮痛剤を処方させていただいております。また、矯正治療を開始した際の歯の移動に伴う痛みもありますので、当院では矯正治療開始時と抜歯を同時に行うことが多いです。 (ご希望があれば別の日程にさせていただくことも勿論可能です)
- 不適切な計画では口元が平坦になりすぎることも
あまりに前歯を引っ込めすぎると口元が平坦になる場合もありますので、審美的にも満足いくような計画を当院では立案するようにしています。
まとめ
矯正治療における抜歯は、「不必要な犠牲」ではなく、「歯列・咬合・顔貌・歯周組織の長期的健康を守るための計画的手段」です。
顎と歯のバランス、審美的要求、機能的安定性を総合的に判断し、最適な治療方針を選択することが重要です。
非抜歯で可能なケースも増えていますが、無理な非抜歯治療は将来的なトラブルの原因となるため、適応判断が何よりも大切です。個人個人で治療計画は変わりますので、一度当院までご相談下さい。

津田歯科・矯正歯科の医院情報
津田歯科・矯正歯科
住所:大阪府大阪市都島区善源寺町1-5-37 美代志ビル1階
アクセス:大阪メトロ谷町線「都島駅」より徒歩3分
電話:06-6922-6480
Web予約:https://tsuda-dc.jp/当院のInstagramはこちら:https://www.instagram.com/tsudadentalclinic5824/
診療時間:平日 9:30~13:00 / 14:00~18:00
土曜 9:30~13:00 / 14:00~17:00
休診日:木曜・日曜・祝日(GW・お盆・年末年始あり)
CATEGORYカテゴリー
RECENT POSTS最近の投稿
TAGタグ
ARCHIVE月別アーカイブ
2026年 (4)
2025年 (233)
2024年 (205)
2023年 (49)
2022年 (11)
2021年 (1)
2020年 (9)
2018年 (24)
2017年 (64)
2016年 (49)
2015年 (12)