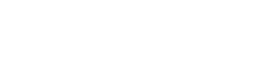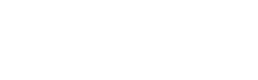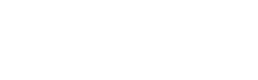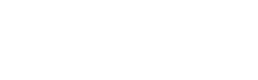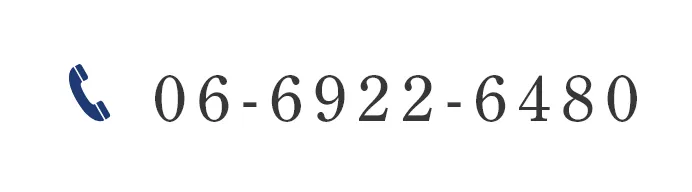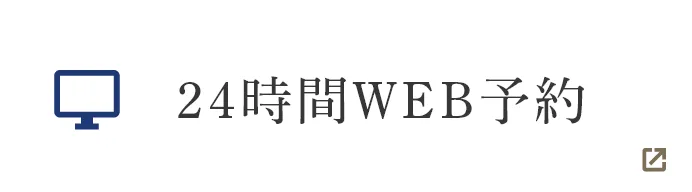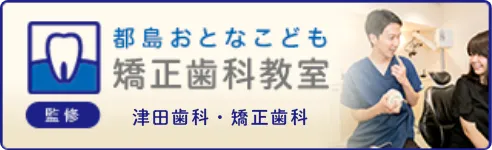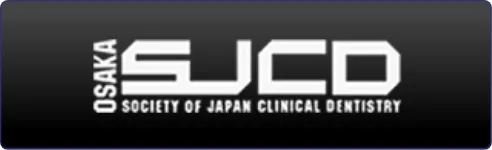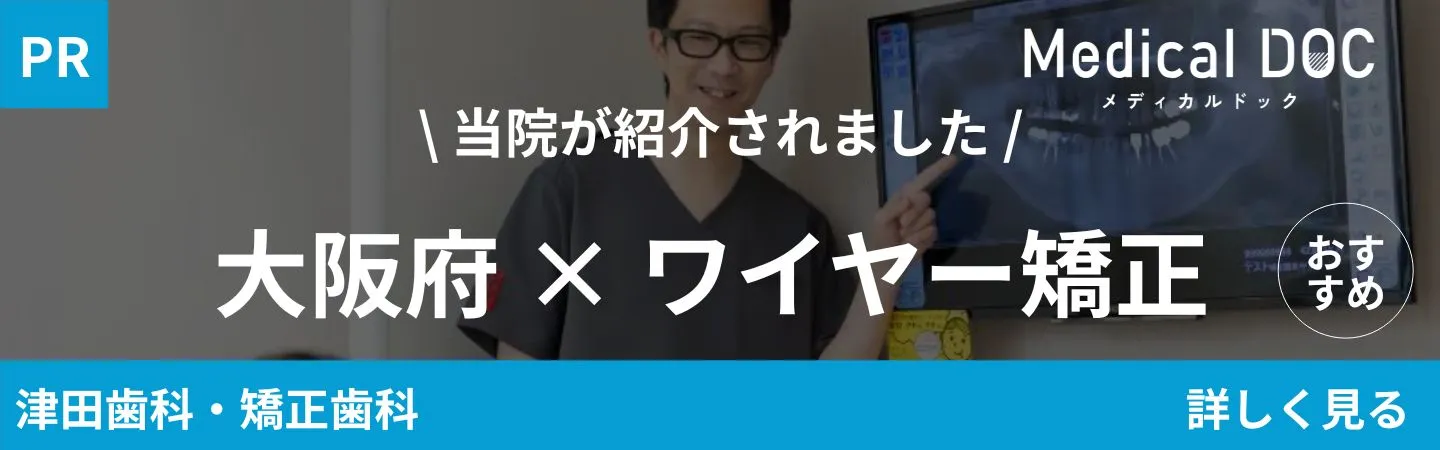スタッフブログ
【都島区で入れ歯を検討中の方へ】保険診療の入れ歯を選ぶ前に知っておきたい“3つのリスク”
保険診療の入れ歯に潜む“見えないコスト”とは?
「保険診療の入れ歯は安いから安心」と思って選んだはずなのに、
実際に使い始めてみると、「痛い」「外れる」「噛めない」「見た目が気になる」といった不満を感じる方は少なくありません。
一見“安く済んだ”ように見えても、作り直しや再調整を繰り返すことで結果的に高くついてしまうケースも多く見られます。
また、合わない入れ歯を無理に使い続けることで、顎の骨がやせてしまい、次に入れ歯を作るときにさらにフィットしづらくなるという悪循環も起こりやすいのです。
このように、「安いから」という理由だけで保険診療を選ぶことには、“見えないコスト”が潜んでいるといえます。
保険の入れ歯が「合わない」と感じる理由
保険診療の入れ歯は、全国どこでも同じルールで作られるため、使用できる材料や製作工程に制限があります。
具体的には以下のような点が挙げられます。
レジン(プラスチック)製で分厚くなる
→ 壊れにくくするために厚みが必要になり、違和感や発音のしづらさが生じます。金属を使えない(※部分的に使える場合もあり)
→ 薄く作れず、熱が伝わりにくく、食事の楽しみが減る。製作にかけられる時間が限られている
→ 技工士が模型上で短時間で作業を行うため、微細なフィット調整までは難しい。
このような制約の中で作られるため、一人ひとりの口腔状態に完全に合わせた設計は難しいのが現状です。
「なんとなく合わない」「噛むと浮く」「口の中でカタカタする」といった症状が出やすいのは、こうした構造的な理由があるからです。
合わない入れ歯を使い続けることのリスク
入れ歯が合わないと、「食べにくい」「話しづらい」といった不便さだけでなく、お口や全身の健康に悪影響を与えることもあります。
1. 顎の骨がやせる(骨吸収の進行)
入れ歯が合っていない状態で噛むと、特定の場所に過剰な圧力がかかります。
その結果、骨が刺激を受けて吸収が進み、顎の形そのものが変わってしまうことがあります。
2. 噛み合わせのバランスが崩れる
左右どちらかでしか噛めなくなると、顔の筋肉のバランスが崩れ、顎関節症や肩こり・頭痛を引き起こす原因にもなります。
3. 消化機能の低下・栄養不足
入れ歯でしっかり噛めないと、食事の選択肢が偏り、咀嚼不足によって胃腸への負担が増加します。
高齢の方では特に、栄養バランスの乱れがフレイル(虚弱)や誤嚥性肺炎のリスクを高めることもあります。
精密義歯(自費診療)との違いは「時間」と「精度」
一方で、自費診療の入れ歯(精密義歯)は、使用できる材料や設計方法の自由度が高く、
1人ひとりのお口に合わせた“オーダーメイド”の治療が可能です。
たとえば、当院のように精密な型取りを重視する場合、
噛み合わせや筋肉の動き、発音時の舌の位置などを細かく記録して製作を行います。
その結果、吸着性が高く、ズレにくい入れ歯を作ることができます。
また、金属床義歯のように熱伝導率の高い素材を用いると、
「温かい」「冷たい」といった食感をしっかり感じられ、自然な食事の楽しみを取り戻せるのも大きなメリットです。
入れ歯治療は「安さ」ではなく「人生の質」で選ぶ
入れ歯は“失った歯の代わり”ではありますが、単なる「モノ」ではなく、
**毎日の生活を支える“体の一部”**です。
合わない入れ歯でストレスを抱えながら生活することは、
「人と食事を楽しむ」「会話をする」といった**人生の質(QOL)**を下げてしまいます。
一方で、自分にぴったり合った入れ歯は、
見た目にも自然で、しっかり噛める・痛くない・話しやすいといった快適な日常を支えてくれる存在になります。
津田歯科・矯正歯科では、保険・自費の両方を理解したうえで、
患者さま一人ひとりのご希望に合わせた最適な選択肢をご提案いたします。
当院が大切にしている「入れ歯のフィット感」へのこだわり
当院では、保険・自費を問わず、入れ歯治療において以下のプロセスを大切にしています。
丁寧なカウンセリング
現在の入れ歯の不満点や生活習慣をしっかりお伺いします。
「どんな場面で困るか」「どのような見た目を求めるか」を共有することで、最適な設計方針を立てます。精密な型取りと噛み合わせの再現
口の動きや舌の位置を考慮し、立体的な情報をもとに製作を行います。
この過程が“フィット感”を左右する最も重要なポイントです。試適と調整を繰り返す
完成前に「試し装着」を行い、実際の発音や咀嚼状態を確認します。
微調整を繰り返すことで、完成後の違和感を最小限に抑えます。装着後のメンテナンスフォロー
装着後の数週間~数か月の間に、噛み合わせや粘膜の変化を確認し、
再調整を行うことで長く快適に使える入れ歯を維持します。
まとめ|「保険で作れるから」だけで決めない
保険診療の入れ歯は、確かに費用を抑えられるというメリットがあります。
しかし、その裏側には、耐久性・精度・快適性の制約があり、
長い目で見ると「不便さ」や「再製作のコスト」というリスクを伴うことも少なくありません。
「今の入れ歯が合わない」「保険の入れ歯と自費の違いを知りたい」と感じたら、
都島区の津田歯科・矯正歯科へぜひ一度ご相談ください。
あなたにとって最も快適で健康的な“噛める入れ歯”を、一緒に見つけていきましょう。
津田歯科・矯正歯科の医院情報
津田歯科・矯正歯科
住所:大阪府大阪市都島区善源寺町1-5-37 美代志ビル1階
アクセス:大阪メトロ谷町線「都島駅」より徒歩3分
電話:06-6922-6480
Web予約:https://tsuda-dc.jp/当院のInstagramはこちら:https://www.instagram.com/tsudadentalclinic5824/
診療時間:平日 9:30~13:00 / 14:00~18:00
土曜 9:30~13:00 / 14:00~17:00
休診日:木曜・日曜・祝日(GW・お盆・年末年始あり)
CATEGORYカテゴリー
RECENT POSTS最近の投稿
TAGタグ
ARCHIVE月別アーカイブ
2026年 (8)
2025年 (225)
2024年 (205)
2023年 (49)
2022年 (11)
2021年 (1)
2020年 (9)
2018年 (24)
2017年 (64)
2016年 (49)
2015年 (12)